投資に興味はあるけれど、「損をしそうで怖い」「仕組みが難しい」と不安に感じていませんか?私自身も以前は同じように迷い、なかなか最初の一歩を踏み出せませんでした。
しかし、今はインターネットの普及に伴い、少額から始められる商品や手数料の無料化等が充実したため、個人投資家にとって投資しやすい環境になっています。特に2024年から始まった「新NISA」は、投資の利益が非課税になる制度として、将来の資産形成を強力にサポートしてくれます。
この記事では、新NISAのメリットとデメリット、証券口座の選び方までを初心者向けに分かりやすく解説します。まずは新NISAの全体像をつかみ、資産づくりの第一歩を踏み出しましょう。
新NISAとは?初心者向けにわかりやすく解説
新NISAとは?
NISAとは非課税投資を行う口座のことで(以下、旧NISA)、その旧NISAがアップデートして2024年から始まったのが、新NISAです。以下、新NISAの特徴を記載します。
新NISAを始めるメリット
① 無期限で税金を払う必要がない
NISAそのものの最大のメリットは運用益に対して、税金がかからないことです。旧NISAと新NISAの違いは、非課税保有期間について最長20年だったものが、無制限に変更になりました。
【具体例】
25歳から65歳まで、毎月3万円を積み立てて年3%で運用した場合のシミュレーションです。
・元本(積立総額):14,400,000円
・運用益:約13,115,698円
・合計(65歳時点の資産):約27,515,698円
つまり、40年間コツコツと続けると元本の約2倍近い運用益が得られ、2,700万円超の資産を作れる計算になり、この運用益をすべてもらえるということになります。
②投資枠の拡大
旧NISAでの制度が「つみたてNISA」と「一般NISA」の2つ存在し、投資枠は年間でそれぞれ40万円と120万円でした。一方、新NISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つが設けられ、年間でそれぞれ120万円と240万円へと拡大されています。
また保有限度額にも変更があり、旧NISAでは最大で、つみたてNISAが800万円と一般NISAが600万円でした。一方新NISAへアップデートされて以降、最大1800万円保有できます。なお、つみたて投資枠と成長投資枠の併用は可能で、成長投資枠は最大1200万円です。
③他サービスとの連携が可能
新NISA口座で取引する際に、他サービスのポイント連携できます。例えばクレジットカードを利用して投資をしたときにポイントを活用することが可能です。日常で買い物するときに貯めたポイントを使って資産形成ができるため、無理なく投資することが可能になります。詳しく「ポイント連携」の箇所で説明します。
新NISAを始めるデメリット
① 値下がりして損した場合、税金の控除はできない。
NISA口座で損失が出た場合、投資によって発生した同一年分の利益とNISAで出た損を相殺することはできません。また翌年以降に損失を繰り越すこともできないので、注意が必要です。
② 1人1口座のみ所有可能
NISA口座自体が税制優遇されているため、1人が複数の口座の作成は禁止です。また金融機関側でも口座開設時に本人確認を行うチェックは厳密に行われているため、仮に複数の口座を同時開設しようとしても、手続きの遅い方はキャンセルされる仕組みとなっています。
「メリットだけじゃないんだな」と知っておくことが大事です。
新NISA口座を開設する前にチェックしたいポイント
取引商品枠
① つみたて投資枠
金融庁が基準を定めた長期・積立・分散に適した商品だけが対象です。主に投資信託やETFで、種類はインデックス型・アクティブ型・ETFの3つあります。
インデックス型は市場平均に連動し、低コストで安定的な運用が可能です。アクティブ型はファンドマネージャーが銘柄を選んでインデックス型以上の成果を狙うものです。ETFは株式や債券などをまとめてひとつのパッケージにし、株と同じように市場で売買できる金融商品ですが、対象数は少なく2025年時点で8本に限られています。
② 成長投資枠
自由度が高くリターンを重視した投資が可能で、対象は株式、ETF、REIT、投資信託の4種類です。
株式は東証などに上場している会社の株式のことで、配当金や株主優待を狙えることや将来有望だと思う産業に直接投資できます。ETFは幅広い上場銘柄から選ぶことが可能で、商品によっては配当や分配金も得られる場合もあります。REITは投資家から集めた資金でオフィスビルや商業施設、マンション等に投資を行うことで、賃料収入や売却益を分配する仕組みです。投資信託については、条件付きで投資家から集めた資金を運用会社が株や債券に投資する仕組みです。
取引手数料
NISA口座での手数料は無料の会社が多いです。特にほとんどのネット証券会社は無料です。以下代表的な証券会社の比較表です。
| 証券会社名 | 国内株式取引手数料(NISA口座) | 米国株式取引手数料(NISA口座) | 投資信託購入手数料(NISA口座) | ETF取引手数料(NISA口座) |
| SBI証券 | 無料(日本株) | 無料(米国株・海外ETF) | ノーロード(購入手数料無料) | 無料(海外ETF) |
| 楽天証券 | 無料(日本株) | 無料(米国株・海外ETF) | ノーロード(購入手数料無料) | 無料(海外ETF) |
| マネックス証券 | 無料(日本株・米国株) | 無料(米国株・海外ETF) | ノーロード(購入手数料無料) | 無料(海外ETF) |
| 松井証券 | 無料(日本株) | 無料(米国株・海外ETF) | ノーロード(購入手数料無料) | 無料(海外ETF) |
| GMOクリック証券 | 無料(日本株) | 無料(米国株・海外ETF) | ノーロード(購入手数料無料) | 無料(海外ETF) |
| PayPay証券 | 無料(日本株) | 無料(米国株・海外ETF) | ノーロード(購入手数料無料) | 無料(海外ETF) |
他社ポイントとの連携
一部証券会社でポイントと連携している会社があります。以下具体的な内容を紹介するので、比較表をご覧ください。
| 証券会社名 | 特徴・備考 |
| SBI証券 | クレカ積立対応、ポイント還元あり(Vポイント、PONTA、dポイント、JAL、Paypayポイント) |
| 楽天証券 | 楽天ポイント利用可能 |
| マネックス証券 | クレカ積立対応、dポイント還元あり |
| PayPay証券 | PayPay連携でのポイント還元あり |
新NISAのおすすめ口座3選
SBI証券
ネット証券の最大手で、口座開設数は業界トップ水準です。「ゼロ革命 × NISA」を掲げ、国内のみならず、米国株式や海外ETF、投資信託の売買にかかる手数料はかかりません。
取扱商品に関して、つみたて投資枠で271本、成長投資株で1371本(両方とも2025年3月10日時点)の銘柄を取り扱いがあり、つみたて投資枠については投資信託のみに対して、成長投資枠は国内と海外に分かれます。国内は株式とJ-REIT、ETFの3つに対して、海外は株式とETFを取り扱いがあり、取引単位は1株から売買可能です。
つみたての場合、三井住友カード積立でカード利用金額に応じて、最大4%ポイントが付与されます。また投資信託のつみたては100円から可能です。大手銀行だと最低1000円は必要なのに対して、投資初心者にとっても始めやすいのが特徴です。
楽天証券
SBI証券と並びネット証券の最大手で、口座開設数は業界トップ水準です。国内のみならず、米国株式や海外ETF、投資信託の売買にかかる手数料はかかりません。
取扱商品に関して、投資信託は2560本、国内株式は4420本、米国株式は4666本(すべて2024年4月19日時点でNISA取引外あり)の銘柄を取り扱いがあります。つみたて投資枠については投資信託のみで、金融庁が定めた一定の水準を満たした商品に限定されている為、長期や積立投資に適した商品です。また保有中にかかる管理費用は低コストとなっています。成長投資枠は新規公開株を含む国内株式や米国や中国等の海外株式、毎月分配型やヘッジ目的以外でデリバティブが組み込まれた投資信託が挙げられ、取引単位は1株から売買が可能です。
つみたて投資の場合、楽天カード決済の積立の場合、1年間で最大27000ポイントが還元されます。また投資信託のつみたては100円から可能の為、投資初心者にとっても始めやすいのが特徴です。
その他金融教育にも力を入れているのが特徴で、無料で真鍋素サービスが多数あります。具体的には、おすすめのマネーの本や雑誌を無料で提供している「楽天Kobo」やお金の勉強ができる「トウシル」、投資デビューから次のステップへのプログラムを年間で用意している「資産づくりカレッジ」が該当コンテンツです。お金の知識に自信がなく、経済指標が分からない投資初心者にとってはNISAの始め方を丁寧に教えてくれるサービスになっています。
マネックス証券
日本を代表する総合ネット証券会社の一つで、主に米国株取引に強みを持っています。NISA口座内でのすべての取引(日本株・米国株・中国株・投資信託)において、売買手数料が無料です。また単元未満株の売却、米国株の売買時の国内取引手数料などの手数料に関する消費税もキャッシュバックの対象です。
取扱商品について、つみたて投資枠で272本の取り扱いがあります。インデックスとしてはS&P500やオルカン日経平均といった主要インデックスを取り扱った商品です。一方成長投資枠については、国内の公募投資信託、国内外の株式、ETF、国内REIT などがあります。ただし信託期間20年未満の商品や毎月分配型や過度なデリバティブ使用のある投資信託は対象外です。取引単位は1株から売買が可能です。
アカウント連携について、dアカウントと連携しておくことで保有ポイントをdポイントとしてもらうことが可能で、約定金額の最大 1.1% がマネックスポイントとして還元されることがあります。またクレジット積立にも対応しており、月10万円まで対応することが可能です。
新NISAを始める前に知っておくべき注意点
投資は「余裕資金」でやる
自身での財産状況を確認していただき、失ってもいい金額を証券口座に投入しましょう。そうは言ってもその基準が分からないという方は、月1万円程度で始める積み立て投資がおすすめです。
短期の利益を狙うより「長期でコツコツ」が大事
デイトレードのようにボラティリティ(値動きのこと)を生かして資産を伸ばすのはリスクが大きいため、投資初心者は月額で少額からコツコツ運用していくことがおすすめです。
商品選びは分散してリスクを抑える
特に成長投資枠で株式を購入する場合に注意なのですが、1つの銘柄に集中投資して価格が下がった場合は、塩漬けになりかねません。すべての銘柄が常に上昇していくわけではないので、分散して投資することがおすすめです。
まとめ
新NISAは、初心者にとっても資産形成をスタートしやすい制度です。まずは税金や投資枠、他ポイントとの連携といったメリットとデメリットを理解していただいたうえで、どの証券口座で解説するのかを決めましょう。基準としては銘柄数や手数料、普段使っている他社ポイント制度(Vポイントや楽天ポイント、dポイント)等を確認して総合的に判断するのが望ましいでしょう。いきなり投資するのは難しいと思うので、まずは無料なので口座開設からでも問題ないと思います。投資について学習して少額から始めれば、きっと資産を増やすことができるでしょう。

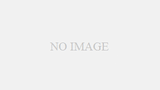
コメント